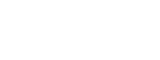ベアフットシューズの走り方-正しいフォアフット

ベアフットシューズを履いたら、通常のシューズと同じように走るわけにはいきません。正確に言えば、ベアフットシューズを履くだけで走り方は変わります。
踵に厚みがないので、自然に走ろうとすればフォアフット気味で走ることになります。
しかし、これだけでは不十分です。
フォアフット接地は自然の中で生まれ育っていれば自然に身についたはずの動きです。米国の理学療法士、ケリー・スターレットは「幼稚園入園前の子供たちは、まるで小さなケニア人ランナーのようにフォアフットで走っていた。しかし、小学一年生になるころには半数がヒールストライク(踵接地)になっていたと」と記載しています。
入園前以降、正しい走り方ができていないわけなので、それこそ赤ん坊が歩き方を学ぶように、しっかりと学ぶ必要があります。
心配はいりません。正しい知識とベアフットシューズがあればすぐに身につけられますよ!
つま先は(ほぼ)下げない

つま先はほぼ下げない。足首はリラックスさせ、着地の際に地面とできるだけ平行にして接地します
フォアフット=足の前側だからといって、つま先着地と表現されることがありますが、「つま先接地」という言葉は誤解を招く表現なので私は使いません。
つま先接地というと、つま先をあえて下に向けて接地する人がいます。
しかしつま先を大きく下に向けると、指の付け根と指が同時に接地してブレーキがかかってしまいます。
地面に触れた瞬間は、指は浮いているようにしなければなりません。
足首の力を抜いて自然に接地すると、つま先は若干下向きになります。
長距離走では、この自然な角度で十分です。
足首をリラックスさせたまま下し、着地の際に地面とほぼ平行にします。

指が上げて、足は地面とほぼ平行にして接地(参考:The Barefoot Professor. Nature Video(*1))
短距離走、ラストスパートなど、スプリント走のスピードを出すときは、つま先が下がらないように意識し、足首を固めて接地します。
つま先が上がるほど、地面の反発が強くもらえますし、ブレーキもかからなくなります。
小指側、小趾球から接地する

小指側、小趾球から接地します
地面に最初に触れるのは、小指の付け根にあるふくらみ、「小趾球」と呼ばれる部分です。
親指付け根のふくらみは「母趾球」といいます。
母趾球から接地すると解説しているところもありますが、母趾球接地は不自然ですし、怪我にもつながります。
母趾球より小趾球が自然であることは簡単に確認できます。足首の力を抜いて膝を上げてみてください。
足は小指側に傾くはずです。無理に力を入れない限り、足は小指側から地面に触れるのが自然であることの証です。
小指側から接地すると、足首が内側に倒れるように動くことで接地面が親指側へと広がっていきます。この内側にひねる動きを日本語で回内(かいない)、英語でプロネーションと呼びます。ランニングや陸上の世界ではプロネーションと呼ぶのが一般的です。
プロネーションはよくない動きだとして矯正するシューズもありますが、プロネーションは衝撃吸収のための欠かせない動きです。
足の小指側が触れ、そこから徐々に内側が触れていくことで衝撃が吸収されます。
母趾球と小趾球が同時に接地するのもおかしいです。これはプロネーションが起こらないだけでなく、足の横アーチの機能を正しく引き出せません。
接地について詳しくは「正しい足の接地順序-ケガしないフォアフットのために」で説明します。
つま先を下げずに小趾球から接地することで、自然に緩やかなプロネーションが起こり、柔らかく接地ができます。
マラソンで人類初の2時間切り(非公認形式)を果たしたエリウド・キプチョゲも小指側、小趾球から接地しています。
膝(ひざ)を曲げる

膝はしっかり曲げて、衝撃を吸収します
踵から接地する場合、どうしても膝が伸びます。
踵から地面をとらえようと、踵を前に出すと膝を伸ばす必要があるからです。
立った状態で、片方の足を前に出して踵から地面についてみましょう。膝が伸びているはずです。
その状態でフォアフット接地に変えてみましょう。膝が曲がるはずです。
このように、フォアフットで走れば自然と膝は曲がります。
膝が曲がった状態で走ることが正しいランニングフォームです。

よく見かける、膝を伸ばして走る間違ったイメージ画像
膝が伸びたイラストやイメージ写真があり、一見綺麗に見えますが、膝が伸びていては膝に大きな衝撃がかかり怪我をしてしまいます。
フォアフットなら、膝は自然に曲がりますが、曲がりが足りないことがあるので、最初のうちは意識的に曲げてください。膝のクッションが生かせるだけでなく、下腿(膝から下)が受ける衝撃が減り、推進力も生み出しやすくなります。
膝を曲げることによるメリットについて、詳しくは、「走るとき・歩くときに膝を曲げるべき科学的理由」で解説します。
足を引いて優しく接地する
着地の際、足を地面にたたきつけるように強く踏み込むのは厳禁です。
短距離は地面の反発が大きいほうが有利なので、弾むボールのように強く接地しますが、このような走り方は長距離では不可能です。
強く接地すると、その分ブレーキも大きく、足への衝撃も大きいです。
踵着地の場合、接地時には体重の3倍もの衝撃が加わっています。
それに比べて、マラソンの元世界記録保持者であるパトリック・マカウが受けている衝撃は体重の1.2倍程度でした(*2)。

足を上げ平行に、同時に若干引くことで衝撃と速度差を吸収します
マカウはフォアフットのうえ、着地の瞬間に足を地面と平行にし、足を引くような動きを入れます。
これにより地面との速度差を無くし、同時に足の落下速度を遅くして、接地の衝撃を軽くしています。
アメリカのベアフットランナー、ケンボブ・サクソンは「接地するときに足を少し上にあげる」ことを勧めています。
これもマカウの動きと同じく、着地の衝撃を軽減するための動きです。
この柔らかい接地により、足の筋肉の活動を半減できることがわかっています。同じ距離を走っても、足の筋肉の疲労は半分というわけです。
最初に紹介した、「つま先は(ほぼ)下げない」フォームはここにも関わってきます。足首はリラックスさせたまま足を下ろし、着地の瞬間に地面と平行になるように少し上げ、そして足を引きながら接地、という流れになります。
接地について、詳しくは「マラソン世界記録に学ぶ究極の接地方法」で解説します。
フォアフットで走っても、つま先から強く地面に接地していては、その効果も半減してしまいます。
大股で走ろうとしない
よく「大股で走る=ストライドが大きい」と勘違いされていますが、ストライドと股関節を開くことは別物です。
フォアフット接地は体の真下に接地する(前に進んでいるので、実際には体の若干前で接地し始める)ので、前側の足はいつも同じ位置にあり、これ以上大股にする意味はありません。
ストライドが大きいというは、一歩でより遠くまで跳ぶということです。これはどれだけ強い反発を生み出せるかということなので、股関節の開き具合とは無関係です。
大股にしようとすると、当然エネルギーの消費は増えますし着地の衝撃も強くなるので、むしろ歩幅を開きすぎないよう意識しましょう。
フォアフットが正しくできるようになれば、あとはスピードをあげればストライドも大きくなります。
ベアフットシューズの正しい走り方まとめ
- つま先は(ほぼ)下げない
- 小指側、小趾球から接地する
- 膝を曲げる
- 足を引いて優しく接地する
- 大股で走ろうとしない
参考文献
*1. The Barefoot Professor; Nature Video, 27 Jan 2010
*2. 42.195km科学 マラソン「つま先着地」vs「踵着地」, NHKスペシャル取材班, 2013